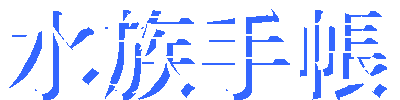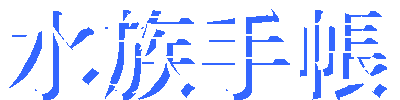水族手帳
動物園には動物が、植物園には植物が、そして水族館には「水族」がいる。いびつな人工空間をたゆたう水族たちは、海や川に住む生き物とは似て非なるものだ。
かれらはけっして人間を歓迎してはくれない。かれらとぼくらの間は厚いアクリルガラスで隔てられ、ふたつの心がわかりあうことは絶対にない。でも、それでも、ぼくらはかれらに会いに行く。かれらがぼくらを必要としていなくとも、ぼくらにはかれらが必要だから。
ここはなんといっても館内に据えられた巨大な回遊槽がいい。円い壁面いっぱいの水槽を、カツオやブリなどがものすごい速さで泳いでゆく。それを見ているだけで何時間も過ごせそうな気がする。そして実際、そうやって何時間も過ごす。
水槽の下に目をやると、傷つき、あるいは力つきて回遊から脱落したさかなが何匹か沈んでいることがある。がんばれ、とは言わない。かわいそう、とも言わない。言えるはずもない。
回遊槽を抜け、「さわれる磯の生物」のコーナーを抜け、短期のイベントコーナーを抜けると、そこでようやく外に出る。潮風に髪をめちゃくちゃにされて、ふとこの施設が本物の海にひどく近い場所にあることを思い出す。濃厚な大洋のにおいをたっぷり含んだこの強烈な風は、けっして館内に吹いてくることはない。(19960211)
もくじへ タイトルページへ
水族館の定義を「人工自然」とするなら、ここは半分外れている。この施設はすばらしく「人工的」で、しかし「自然」からはもっとも遠い。小さな水槽の中にぎっしりと詰め込まれた宝石みたいな熱帯魚。柱時計のギミックのようにくるりくるりと踊り続けるパンダイルカ。ここは水族たちのショーウィンドウだ。そのいとおしいつくりもの臭さは、この施設が都市のただなか(しかも一番高いビルの上!)にあることともちろん無関係ではない。
ぼくらは街で映画を観、ハンバーガーを食べたあとで、マンボウに会うことができるのだ。水槽の内側に張られた衝突防止用ビニールシートのたるみが作り出す、ゆがんだマンボウでよいのならば。(19960213)
もくじへ タイトルページへ
入口をくぐって薄暗い館内(暗くしてあるというより、電気がもったいないので消しているという暗さ)に入ると、実に地味なさかなが出迎えてくれる。いかにも動物園併設の水族館らしくてうれしくなる。順路に沿って歩くにしたがって、さかなのバリエーションはだんだん増えてくる。でもやっぱりどれもこれも地味だ。
館内を二階三階と進んでゆくと、ふと妙なことに気づく。いつのまにか、自分が見ているものがサンショウウオだのカエルだのにすりかわっているのだ。展示がおかしくなってきたのは、あの肺魚を見たあたりか。もしかして隣に両生類館なんてのがあって、そこに迷いこんだのかも……。
わけもわからず、とりあえず歩いてゆく。と、突然視界が明るくなる。そこは広いフロアで、天井から陽の光が入るようになっている。その中央にのんびりと鎮座しているのは巨大なワニ。そして、ワニの肩越しに「水族館出口」の表示が見える。
つまり、われわれはさかなから爬虫類にいたる進化の過程を見せられていたのだ。地味だと思っていたらこの演出。さすがは動物園の水族館だ。一本とられた。
外へ出る。眼前に広がるのは檻に入れられた鳥類や哺乳類、そしてそれを見ているヒトの群れ。たくらみはまだ続いている。もう「おみごと」としか言いようがない。(19960213)
もくじへ タイトルページへ
名古屋というのは不思議な街だ。整然と区画された街並みは機能美にあふれているのに、それを自ら解体するような「下世話」がトラップのように散りばめられている。思想なく配置されたオブジェ、市庁舎ビルの屋上に鎮座する天守閣、無骨なテレビ塔。どうもこの街は「周りによく見せたい」という情熱がしばしば空回りする傾向にあるように思える。
それは名古屋港も同じだ。名古屋港には市民の憩いの場、あるいはデートスポットに必要なものがすべてそろっている。公園。展望台。遊覧船。そして水族館。だが、どれもが少しずつ「ズレ」ている。展望台は言われなければわからない「船のマスト」型だし、遊覧船は「金のしゃちほこ」だし。
名古屋港水族館は、南氷洋の海洋生物をメインに据えたテーマ性の高い施設だ。規模はそれなりに大きい。深海探査船の擬似体験など、趣向を凝らした展示もある。だがひととおり見回ると、どこか心にひっかかりが残る。
その理由はどうやら、展示の「理科室」性にあるようだ。この水族館にはなぜか「実験コーナー」的な水槽が多い。解剖した生物のホルマリン漬けもある。展示物をよりわかりやすく見てもらいたいというこの水族館側の想いは、しかし訪れる客の期待とは相容れない。客が見たいのは「元気に生きている海の仲間たち」なのだから。
だがもしかすると、この名古屋の水族館こそが「真の水族館」なのではないかとも思う。水族館とはふつう見られない水中の生き物を「見たい」と熱望する人間が作り出す特殊な空間であり、その意味では「南氷洋から日本に連れてこられたさかな」も「内臓を開かれて標本にされたさかな」もともにその目的にかなった「水族」の姿には違いないのだ。(19960217)
もくじへ タイトルページへ
葛西臨海水族園と同じく、ここの水族館にも巨大な回遊漕がある。だが訪れる者にとって、この二者はまったくの好対照を見せる。
葛西の水槽は「見上げる」海。観客はありえない海底から、ありえない海面を深海魚のように望む。ただそれだけ。
それに対して海遊館の水槽は、「見下ろす」ことができるのだ。数階分をつらぬく巨大な特殊アクリルガラスの海は、その最上階において目も眩むほどの深淵(アビス)を現出させる。ぼくらはそこから、水族たちのたゆたう世界へと落ちていく。
順路は上から下へと設定されているので、観客はみな落下を義務づけられる。あえて順路を逆行しないかぎり、水面に還ることはできない。
順路が終わり、水底へたどりつくころ、ぼくらはそこに見るかもしれない。海面から落ちてきた、もうひとりの自分の姿を。(19960520)
もくじへ タイトルページへ
イルカのいる水族館は、ちょっと苦手だ。
イルカ教の信者というわけでは、もちろんない。「水槽の熱帯魚はいいけれどイルカショーはいや」ということがどれだけ矛盾しているかもわかっている。しかし、ショーの合間水槽で待機しているイルカたちの顔に、ぼくはついある表情を読み取ろうとしてしまうのだ。
しながわ水族館にも、芸達者なイルカがいる。かれらの芸が見事であればあるほど、ぼくの心の底からなにか忸怩たる思いが沸き上がってくる。
だがそんな思いを相殺してくれる展示が、この施設にはある。それは入り口にある「江戸前の魚たち」だ。ここに泳いでいるのは、まごうかたなき「寿司ネタ」である。このユーモラスなまでに下世話な展示が、自分のつまらないこだわりをやわらげてくれるような気がする。そう、ぼくらはキスやサヨリの味を愛し、イルカの芸を愛していればよいのだ。それ以上いったいなにができるだろう。水槽のイルカにどんな表情を見たとしても、そこからかれらの情動を察し、共感することなどわれわれにはできないのだ。われわれはかれらとは別のいきものなのだから。
すべての水族は平等である。水槽の外に群がる、このニンゲンといういきものの前において。(19961031)
もくじへ タイトルページへ
タイトルページにもどる
copyright(C)1996-2009 FUJII,HIROSHI all rights reserved.