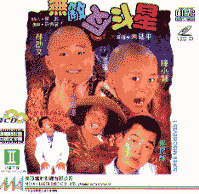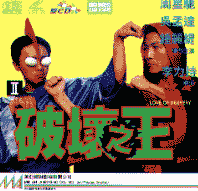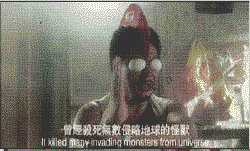チャリティに「がんばり」は必須か?
まだちょっと本職がバタバタしているので、今回はちょうど1年前の今ごろに書いた文章をちょっと修正した上で掲載させていただく。要するに手抜きなわけで、まったく申し訳ない。しかしワタシは、それよりも1年前の文章がほんの少しの修正で今年にもほぼ完全に通用することに対してとても驚いている。
8月の最後の週末、断続的に「24時間テレビ」を観ていた。愛が地球を救うあれである。最後まで観ていないので今回どれほどの募金が集まったのかは知らないのだが、昼ごろ
の時点で1億数千万と言っていたので最終的にはかなりの金額になるのだろう。
しばしばこの番組に対して言われる「偽善的」であるとの意見には、ワタシは与しない。たしかにテレビ局にも利益があるからこそこういう企画をやっているのだろうが、実際に収益がさまざまな福祉の役に立っているのはまぎれもない事実であり、その点で「なにもしない」ことよりは当然ずっと賞賛されるべきことだ(そもそも日本人は安直に「偽善」ということばを使いすぎる。正確な定義----これは本来キリスト教の用語だ----をわかっている人間がいったいどれくらいいるのだろう)。
だが、それでもなお、この番組には視聴者をして「なんかちょっとねえ……」と思わしめるモノがある。その原因はなんだろうと考えていたが、しばらく観ていればすぐにわかった。
みんながんばりすぎなのだ。
困難な状況に立ち向かって生きる人やボランティアに汗を流す人の姿は、それなりに感動的である。だがこの番組が示す「がんばり」には、そういったものとは微妙なズレがあるように思える。死にそうになりながら100キロのマラソンを走る赤井英和(しかもその前に何人ものリレー走者がいたという重圧つきで)や、富士山頂を家族づれで登る盲人といったイベントは、どちらかというと「びっくり日本新記録」とか「ギネスに挑戦」とかのノリだ。このようなものを見せられると、なんだか「チャリティーにはこのくらいの根性と覚悟が必要なんだ」と思ってしまう。「献身」とか「自己犠牲」とかいったことばも頭をかすめていく。
ワタシには、こういった過度の「がんばり至上主義」こそが、一般の人間からチャリティーというものを遠ざけているような気がしてならない。人が人と助け合うことはとてつもないエネルギーを要するものだという強迫観念を、この番組は植えつけてはしないか。「すべてを他者への奉仕にささげる」ということと「そこまでできないから、やっぱりなにもしない」ということの極端な2元論に、人々を追い込んではいないか。
そもそも、この番組の「24時間ぶっつづけで放送する」というシステム自体が「がんばり至上主義」の産物である。出演者は放送時間をまっとうする苦痛を口々に語り、そして「でもまだがんばります」と強調する。場には悲壮感すらただよい出し、かくてブラウン管には「チャリティーの戦場」が現出する。
チャリティーというのは、もっと「フツーのこと」であるべきだ。揃いのTシャツを着て愛を謳歌するのは大衆へのアピールという意味では重要なのかもしれないが、あまりに気を張られるとちょっと引いてしまう。人が他者について考える瞬間は、もっといろんなところに広く浅く遍在(偏在じゃなくて)していなければならないと思う。晩ご飯のおかずのこととか、恋人とのHのこととか、月末に発売するはずのマンガのこととか、イヤな上司のこととか、そういうことを考えている頭の別の一角でふと「あの商店街の歩道って車椅子だと通りにくいよな」などと思ったりするのが自然なありかたではないだろうか。崇高な大イベントよりも、今田耕司がケツを出して踊ってる番組が実はチャリティーだったなんて方が、たぶんずっと正しい。
(19960903)
旧よしなしのもくじへ 現よしなしへ
源流さんを探せ!(パイロット版)
●そのいち 「おたく」の源流さん
先日知人の間で、「おたく」という言葉の歴史について話がのぼった。その時のメンツの共通認識は、どうやら「おたくの発案者は中森明夫である」ということで一致しているようだった。たしかにコミュニケーション不全のアニメファンを、二人称に「おたく」を好んで使うことから「おたく族」と称したのは中森明夫である。しかし、ではそもそもアニメファンたちがなぜ二人称に「おたく」を使い出したのか、そこまでちゃんと言及している人や文章は少ない。
「おたく」の直接の源流を作ったのは、作家の新井素子である。
新井素子は現在はぬいぐるみマニアとしてしかその名を聞くことがないが、80年代初頭にさっそうと文壇に現われたSF作家である。全盛期にもまだ大学生だった彼女の作品は、よくできたジュブナイルSFであると同時に、同世代に共感を与える一種のエッセイでもあった(ちなみにデビューは高校在学中である)。そして、その作品の最大の特徴は、常に一人称を「あたし」、二人称を「おたく」とするモノローグ文体だったのだ。これは、当時の「大学生口調(文系の学生全般であり、けっしてアニメマニアに限らない)」を反映したものだと考えられる。
この新井素子を大々的に取り上げたのが、創刊して間もない雑誌「ファンロード(当時は「ふぁんろーど」)」である。同誌が組んだ新井素子特集は、その中心読者であるアニメファン、漫画ファン、同人誌制作者(要するに、後に「おたく」と呼ばれるヒトビト)に大きな影響を与え、多くの「モトコスト・モトコシタン(新井素子ファンのこと)」を作ったのである。同時にそれが、これら読者に「おたく」という二人称を流布させることとなったわけだ。
だから、「おたく」の源流は、新井素子と雑誌「ファンロード」であるということができる。これは間違いない。なぜなら、ワタシ自身が小学六年生のとき新井素子にかぶれて「おたく」を連発していたのだから。うひー。
なお、中森明夫が「おたく族」という言い方を提唱するかなり前に、すでにアニメファンの間では「おたく」という二人称はすたれていたということをつけくわえておく。
●そのに 「やるっきゃない」の源流さん
「やるしかない」を「やるっきゃない」と言う、ただそれだけのことがとてつもない流行語となったことがあった。これは80年代中葉に大躍進を遂げた社会党の土井たか子がキャッチフレーズに採用したため、「やるっきゃないの元祖は土井たか子」だと思っている人も少なくない。だが、もちろんそれは誤りである。
「やるっきゃない」の源流、それは「ミスDJ」の千倉真理である。
「ミスDJ」とは、文化放送系で深夜に放送されていたラジオ番組である。現役女子大生が週替わりでDJをつとめるという、後の「女子大生ブーム」の火付け役となったヒット企画で、全盛期にはかの「オールナイトニッポン」とタメを張るほどの人気であった。で、その水曜日を担当していたのがこの千倉真理。彼女のキャラクターをひとことで言えば「ドジでたよりない女の子」で、オンエア中非常によく失敗をした(第一回放送で30秒あまりも黙っていたという有名な「伝説」すらある)。そのドジな自分をはげますために彼女が使っていたのが、「やるっきゃない!」のエールなのである。
なお千倉真理は英語が得意で、「やるっきゃない英文読解」という受験向き参考書も出版している。この本で彼女のパートナーを務めているのが、ジョイスの「フィネガンズ・ウェイク」を訳出したあの柳瀬尚紀氏であるというのは知らなくてもどうということのない事実である。
……というわけで、さまざまなコトバや事象の知られざる「源流さん」を追求するという企画を現在考え中である。ネタが集まったらコーナーにするつもりなので、もしこれを読んでるみなさんに「わしはこういう源流を知っている」とか「これの源流は何か調べてほしい」というのがあればメールをいただきたい。もちろん、上の「おたく」と「やるっきゃない」の源流考察に対して「いや、わしはもっと“上流”を知っている」というご教授もお待ちしている。
最後に、現在調査中の「源流さん」について。
1)「なんちゃっておじさん」の源流さん
かつて一世を風靡した謎の人物「なんちゃっておじさん」。その源流には「鶴光のオールナイトニッポン説」「タモリのオールナイトニッポン説」「楳図かずお説」「ドリフ説」などがあって混沌としている。さらには「実在人物説」もささやかれており、状況は予断を許さない。
2)「電線音頭」の源流さん
永遠のカルトヒーロー「電線マン」の名とともに知られる「電線音頭」。これは当然伊東四朗・小松和夫の「みごろ! たべごろ! 笑いごろ!!」が源流だと筆者は思っていたのだが、それ以前にも「電線音頭」をコーナーに持っていたバラエティがあるという情報を耳にしたことがある。さらに、「電線音頭」自体は芸者遊びに源流のある由緒正しい音頭であるとも聞く。真相は如何?(19960810)
旧よしなしのもくじへ 現よしなしへ
凶悪犯に「不死刑」を
ワタシは死刑廃止論者である。いきなりで申し訳ないが、さっき友人と電話でこういうハナシになったので今日はこの話題にさせていただく。どのみちいつかは書こうと思っていたテーマだ。
死刑の是非については、現在でも相当の議論が交わされている。死刑廃止論者は罪を死であがなうことの不毛さ、そしてそれが冤罪であった場合の恐ろしさを論じ、そして死刑肯定論者は被害者(とその遺族)の心情を重視する。そのどちらに理があるのかはワタシには言えない(ただしワタシは「死刑による重犯罪抑止論」には絶対に与しない。それは核抑止論と同様の自己破滅的論理である)。しかし、「死」という不可逆的な刑罰を人に与えることができるほどには、現在の司法制度は発達していないというのがワタシの考えだ。
この件については、ワタシ自身がボードリーダーをしているパソコン通信の掲示板(NIFTY-Serve
FQLD1 10番ボード「ボヤキの部屋」)にかつて書き込んだメッセージがあるのでそれを引用したい。これは94年1月、連続殺人犯の勝田被告に死刑宣告が言い渡された直後のメッセージだ。
『凶悪犯に「不死刑」を』
新聞によると連続殺人犯の勝田被告に、弁護側の「死刑制度は違憲」の主張を退けて死刑が言い渡されたとか。ワタシは基本的に死刑廃止論者なのでこの判決は残念だけれど、死刑制度論議が凶悪犯の減刑のために利用されるというのはなにかちょっと違うんじゃないかとも思う。
法律は仕返しのためにあるんじゃないから「死刑でなければ遺族の気持ちが晴れない」というような論法には絶対に与することはできないけれど、たしかに我々は「因果応報」みたいなのをどこかで刑罰に求めているところがあって、だから死刑に対応するほどの重みを持った目的刑がないというのが死刑廃止論に国民的合意を得られない大きな理由になってるんだろう。無期懲役なんておとなしくしてさえすればわりとカンタンにシャバに出られたりするもんな。もっと厳格な、ちょっとやそっとじゃ出てこられない終身刑があればハナシが違ってくるんだろうけど。
それで思いついたヨタ話。凶悪犯罪者には懲役五百年くらいを言い渡して(ここまではアメリカなんかではよくあるけど)、その刑が終わるまでは絶対に死なせないってのはどうか。つまり、死刑ならぬ「不死刑」。最新の医療技術を駆使して寿命が来てもチューブを山ほどつけて生かしちゃう。たとえ肉体が朽ちても、脳髄だけ取り出して無理矢理生かす。死にたくても死ねない状況の中で、受刑者は黙々と自分の罪を反芻し続けなければならない。死刑なんかよりよっぽど効くぞ。
……でもこれって死刑以上に非人道的だよなあ。
これは書いてる最中にも「ムチャクチャだなあ」とは思っていたが、しかしワタシの死刑制度に対する基本的な考え方を盛り込んだ文章である。つまり、死刑には反対だけど、死刑を廃絶するためにはそれ(死刑)に対応するちゃんとした目的刑が整備される必要があるということだ。
具体的にはそれは「非常に厳格な終身刑」である。囚人は外界から隔離されて自らの成した罪を一生反芻することを命じられる。そして特別に改悛の情を認められた者だけが、厳重な監視の元で社会奉仕の任を得る。恩赦や減刑はない。ただ生かしておくだけで、囚人には「死んだ方がマシ」という余生を歩んでいただく。
これがワタシの「死刑廃止論」である。死刑をやりたくて仕方のない人たちにも、気に入っていただけると思うがどうか。もしご不満なら「寝る時は毎晩針の上」とか「食事は三食ともゲロ」とか「とりあえず四肢は切り取る」といったオプションを提示させていただくのだが。(19960810)
旧よしなしのもくじへ 現よしなしへ
最低の話題
最近、「Readme! Japan」という企画に参加した。これは「読み物」を対象にしたインデックスであり、同時にアクセス数を競うランキングでもある。ワタシは別にランキング上位を狙う気はないのだが、「Web上の読み物を集める」という切り口はおもしろいと思った。これを読んだみなさんも、「いまWebで"テキスト"というのはいったいどういう位置にいるのか」を知りたいならぜひこのサイトに遊びに行ってほしい。
(19970624補足:結局、現在は本ページは「Readme」から撤退しております)
ただちょっとビビるのは、この企画の参加規定だ。いわく「最低でも月4回の更新を行うこと」。一応このサイトは読者からの「そこはかとないもの」や「勝手邦題」の更新でこの基準を満たすことができるが、それでもズボラなワタシにはキツい。
いわゆる「日記」を書けば、あるいは毎日でも更新できるかもしれない。話題がなくても「今日仕事場でこんなことがあった」とか「オフでこの人に会った」とか書けばそれでいいんだから。でも、そういうのって人に読ませるもんじゃないと思う。ワタシの中では、それは「最低の話題」だ。この「よしなしごと」で書いているのがそういった「最低の話題」とどう違うのかと言われれば言葉につまるけど、ワタシはとりあえずは「赤の他人でもわかる」ような文章を書くことを第一に考えている。この点で不備があるならワタシは甘んじて受けるから批判してほしい。でもとにかく、単なる自分の行動記録をメディアにたれながすのはイヤだ。
……とかなんとか言いながら、今日のハナシはまさに「日記」なのである。サイテーである。
朝、「別冊宝島」の「いっきにわかるインターネット(たぶんそんなタイトル)」のコラムを書く。なんでも1ページ分スペースが余ったそうで、緊急の仕事である。とりあえず「投げっぱなしメディア・ホームページの危険な誘惑」と題してつらつらと書きはじめる。自分自身のページ制作の反省に仮託して、コミュニケーションを考えないやりっぱなしのページをボロクソにけなす文章を作る。気がついたら規定の文字数の2倍になっていたので思いっきり削って入稿。その後うちのプロダクションの社長に連絡したら「先方はもっと素人の初々しい体験談を求めてたので、この文はボツになるかもしれない」とのこと。とほほ。でもこういうのはよくあることだ。本が出たら立ち読みしてワタシのコラムを探してほしい。もしボツになってたらこのページで公開します。
昼、コアマガジン(「メガストア」という美少女ゲーム誌を作ってるとこ)のインターネット単行本の仕事をやる。紹介するページの中心はやはり2次元美少女のCGサイトだ。あまたある玉石混淆のサイトからよいものを選ぶ作業が続くが、「玉」だけを選んだつもりでもまだ数百のサイトがあって、このジャンルの隆盛を思い知らされる。重いとかオタッキーとかいわれても、やっぱり「絵」は強い。
夜、仕事の合間に母と久しぶりに外食。ちょっと値の張る寿司屋に行く。食中毒騒ぎはやはりこの店にも影響しているようだが、魚介類でO-157に冒されたという報告は今のところない。ふわりとした鱧の落としと、シメたばかりでまだ動いている鰈が絶品。「イチゲンさんにカリフォルニア巻きを作れとか言われて、困るんですわ」と板前。
……ああ、日記って書くのラクだなあ。面白かった? 面白くないよね。あ、いつも面白くないっすか。ごめん。(19960807)
旧よしなしのもくじへ 現よしなしへ
まだ読んでない本の感想文
読める時間があるかどうかもわからないのに、目についた本をかたっぱしから買い込むクセだけはなんとかしたいと思う。本日もなんやかやと買ってしまったのだが、はたしてズボラなワタシはこのうちの何冊に目を通すのだろうか。で、せめてもというわけで、今回のネタはこれらの本の「読前感想文」である。なんやそれ。
『[新版]パラダイム・ブック(C+Fコミュニケーションズ編著 日本実業出版社 2300円)』。80年代に流行ったいわゆる「ニューサイエンス」を俯瞰する本。実はワタシはこの本の旧版(1986年発行)を読んだことがあるのだが、10年を経ての改版の中身には興味がある。擬似科学者とオカルトオタク以外のだれもが「ニューサイエンスなんてやっぱりうさんくさいだけやん」と感づいてしまった現在、その価値をいったいどう再構築していくのだろうか。今パラパラとめくってみると、旧版でうやうやしく扱われていた例の「100匹目のサル」の話が、新版ではかなり慎重に扱われている(ま、ありていに言うと否定しているのだが)。これを柔軟と言っていいのか、日和ったと言うべきなのか。うーむ。
『ミミズのいる地球(中村方子著 中公新書 680円)』。ミミズ研究者による、初心者のためのミミズ学入門。ミミズの分布を調べることで、大陸移動説の傍証も可能になるという。ワタシ、ミミズきらいなんだよなあ。でもこういう「チマチマしたモノを研究するといろんな真理がわかる」っていうハナシは好きなんだよなあ。ミミズ図版が思ったより少なそうなので、ちょっと安心。
『自殺直前日記(山田花子著 太田出版 800円)』。飛び降り自殺した漫画家の山田花子が、生前書いていた日記を集めたもの。サワリの部分は昔ガロの追悼特集で読んだのだけど、これがもうものすごく面白い。ヒトのこわれてくところって、なんでこんなに面白いんだろう。不謹慎だと怒られるかもしれないけど、少なくとも編者である山田花子の父親は気にはしないだろう。でなければ自分の娘の日記をこんな形で出版するわけがない。この本は山田花子という作家の「作品」なのだ。だから、面白ければ笑うのが礼儀というもんだ。ザッと読んでみたところ、たっぷり笑かしてくれそうな手応えがある。読むの楽しみ。
まだまだあるんだけど、ちょっと卑怯な気がしてきたのでここまで。とりあえず司徒劍僑の『超神Z』日本語版と松田洋子の『薫の秘話』から読むか。……あ、どっちもマンガだ。(19960726)
旧よしなしのもくじへ 現よしなしへ
本日の専門誌さん:『アームズ・マガジン』に悪魔の本性を見た!
ワタシは、本屋でときどき自分の趣味とぜんぜん関係のない分野の専門誌を買う性癖がある。それはたとえばトラック野郎専門誌『カミオン』であったり、へらぶな釣り専門誌『月刊へら』であったりするのだが、こういう特定の専門分野を覗き見るのはなかなかに楽しいものだ。
で、今回発作的に購入したのは『月刊アームズ・マガジン8月号』。これはおたく系プラモ雑誌で有名なホビージャパンが発行しているもので、いわゆるエアガンやサバイバルゲームの専門誌である。ワタシはメカメカしたものは嫌いではないのだが、どうもモデルガンとかサバイバルゲームというのは「そのまんま」な気がしてあまりよい印象を持っていなかった。だから、この雑誌を買ったのは純然たる「できごころ」だ。
さて、この雑誌を読んで一番驚いたのは、かの『聖飢魔II』のメンバー、もとい構成員がエアガンのレビューページを持っているということである。聖飢魔IIとエアガンという組み合わせには一瞬驚いたが、よく考えるとけっこう重なるものがあるのかもしれない。デーモン小暮っておたくだし。
で、ワタシが買った8月号には、ベースのゼノン石川とリードギターのエース清水がそれぞれ記事を担当していた。これが、読んでみるとけっこう趣深いのである。たとえば、「H&K
MP5A5 MINI」というエアガン(マシンガンの寸法をつめた、チョロQみたいなデフォルメモデル)について書いたゼノン石川の記事。
「……まさに子供から大人まで、何も考えずに撃って遊べるエアガンなのである。でも本当に何も考えずに銃口をのぞいたり、他人に向けたりするのはいけないのである。なりがおもちゃっぽいと、ついこちらも気を緩みがちであるが、マナーはしっかり守りたいものだ。」
エアガンのマナーを語っている。悪魔が。これには感動した。同じ記事の別の箇所には、こうも書かれている。
「どんなに小さかろうと、またパワーが低かろうと、銃口から弾が飛び出るものは銃であり、取り扱いを怠れば危険なものになってしまう。……」
けだし正論である。ゼノン和尚、ホントはすごくいいヒトなんじゃないのか。いや「いい悪魔」か。「やさしい悪魔」と言っても過言ではない。キャンディーズである。
エース清水はエース清水で、マルゼンという会社のウージーを評してこう書いている。
「……銃だけでなく、競技もひっくるめてひとつのムーヴメントを作っていこうというマルゼンさんの姿勢は、いち悪魔として是非応援していきたいところである。」
悪魔に応援されるモデルガンメーカーというのもどうかと思うが、彼もまたルールとマナーを守ってエアガンを愛するファンのひとりなのだ。実にさわやかではないか。
ワタシは今回思いがけないところで、悪魔の本性を垣間見てしまった。それはつまり、「いいヤツ」だということである。同時に今まで抱いていたエアガンマニアへの偏見も、少し解けたような気がする。ありがとう悪魔。(19960714)
旧よしなしのもくじへ 現よしなしへ
『12モンキーズ』を観に行く
ひさしぶりに映画館へ足を運んだ。目当てはテリー・ギリアムの新作『12モンキーズ』。万難排して行かねばなるまい。
ギリアムと言えばやっぱり『ブラジル』だ。しかしギリアムは『ブラジル(とモンティパイソン)』によってあまりに神格化されすぎているきらいがある。ワタシは今回「『ブラジル』と比べるのはよそう」と心で唱えながら劇場の席についた。『ブラジル』は、映画における一種の奇跡である。同じ奇跡をギリアム作品に毎回求めるのは酷な話だし、それよりこの『12モンキーズ』が『ブラジル』とはまったく違ったオドロキを与えてくれることをこそ期待すべきだろう。
ところが困ったことに、『12モンキーズ』はヘンに『ブラジル』だったのである。「タイニー版『ブラジル』」というか、文字どおり「サルでもわかる『ブラジル』」だ。現実と幻想の混沌としたせめぎあい、管理者(権力者)の醜怪さ、そして絶望と甘美な逃避。細かいところでは音楽の使い方や逃避の象徴としての南国(ブラジル=フロリダ)の位置づけまで、この映画はいちいち『ブラジル』を想起せずには観ていられない。しかし「『ブラジル』的な映画」が、『ブラジル』に勝てるわけはないのだ。
この映画はどうにも『ブラジル』に呪縛されている、と思う。呪縛されているのは観ているおまえの方だと言われるかもしれないが、しかし「ギリアム作品である」ということを完全に視野から外しても、「タイムスリップで人類の危機を救おうとする人間が精神病院に入れられる」とか「現実と妄想の区別がつかなくなって精神的恐慌に陥る」とかいうハナシはもう陳腐ではないか。まあもちろんそこいらの一山いくらの映画よりはよっぽどよくまとまってるし、ピッくんのコワれぶりを鑑賞するだけで充分モトはとれるというものであるが、やはり観た後にもやもやしたものが残る。期待の方が大きすぎたのだろうか。うーむ。(19960703)
旧よしなしのもくじへ 現よしなしへ
そこはかとなき香港ビデオCDの世界
前項で予告したとおり、今回は香港みやげのビデオCDのハナシである。わが国ではいまいちブレイクしないビデオCDであるが、彼国ではかなりの普及率で、屋台なんかでも手に入れることができる(そのかわりLDはあまり広まっていないらしい)。ここに紹介するのはワタシが旺角電脳中心にあるビデオCD専門店で購入した、注目の最新香港映画の数々である。選択基準はただひとつ、「ジャケットがうさんくさい」こと。そこはかとなきC級香港ムービー世界の一端を味わっていただきたい。
『百變星君』


ジャケットを一見しただけで「どういうつもりだ」という思いがこみあげてくるこの作品。ヤクザの情婦に手を出して瀕死の重傷を負わされたおぼっちゃんが、マッドサイエンティストの手で改造され生まれ変わる……というハナシらしい(マジメに観てないのでよくわからん)。改造された主人公は肉体を自在に変形する能力を得て、件のヤクザへの反撃を開始する。このあたりは完全に『マスク』のパクリである。「全片電脳特技挑戦」とジャケットにあるとおりCGが随所に使われていて、けっこうマジで楽しめる。これはひょっとすると傑作かもしれない。バカだけど。
『無敵反斗星』
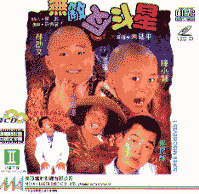

これはもう子役の顔、特にジャケット左の小僧に魅入られて買ったと言ってさしつかえない。イイ味出しまくり。白木みのるもちょっと入ってるし。
ストーリーは盗まれた寺の秘伝書を取り戻すため3人の坊主が冒険の旅に出るというもの(たぶん)で、まあいわゆる典型的カンフーものである。しかしそれにしてもこの主役の小僧、最高。香港映画独特のコビた演技もハマッてるし、カンフーもちゃかちゃかとよく動く。やはり子役は香港映画に限る、ということを再認識させてくれる逸品である。
『破壊之王』
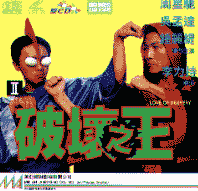
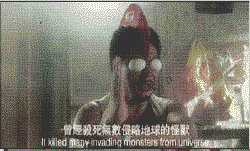
いったいどうしたものか。いい大人が目玉にタマゴはりつけてウルトラマンか。もうすこし落ち着け。
柔道部の女の子にホれたヤサ男が、彼女にアタックするには強くならねばと武道家の門を叩く。ところがこの武道家、ヨーヨーを出して「これは最強の武器だ」と言ってみたり、ヒモにぶらさがってクルクル回って「秘技ローリングサンダーっ!」とか言ってみたり、うさんくさいことこの上ない(しかも「この技の修行は7日コースで1000ドルだ」とかいちいち値をつける)。しまいにはゆでタマゴを切って目に装着、スペシウム光線のポーズをとって「俺様はこれで多くの怪獣を葬ってきた」とのたまう始末。この武道家のもとで修行をつんだ主人公は、はたして彼女の心をつかむことができるか?……って、まあ別にどうでもいいです。(19960630)
旧よしなしのもくじへ 現よしなしへ
シーモンキー全滅
実はこの週末、会社の社員旅行で香港に行ってきた。連日の雨にたたられたが、ワタシは電脳中心でうさんくさい香港映画のビデオCDを買い込むことができたので満足である。このビデオCDに関してはのちほど紹介することにする。
さて、この3泊4日の旅行の間ずっと気になっていたのがシーモンキーだ。ひと月ほど前からシーモンキーを育てはじめたことはすでにご報告したが、これがけっこうとんでもないスピードで成長を重ねていたんである。パソコンの前に置いていたので、もしかすると電磁波の影響かもしれない。ワタシは特に成長した数匹のシーモンキーに「ジュヌビエーヴ」とか「シャルロット」とかの名前をつけて、それはそれは可愛がっていたのだった。
ところが、である。旅行から帰ってきて見てみたら、このシーモンキーがみごとに全滅していた。水槽の底にはなんだか青白いもやもやしたものが堆積していて、よく見ると黒い点々がびっしりと見える。これはどうもシーモンキーの眼らしい。ジュヌビエーヴもシャルロットもあったもんじゃない。
原因はどうにもわからない。シーモンキーは1週間に1、2度エサをやればいい生き物なので、飢えたわけではないはずだ。ひょっとしてこいつらは電磁波を浴びないと生きていけないカラダになってしまっていて、パソコンの電源を落としたせいで死んだのだろうか。とにかく、生き物を飼うことの難しさを久しぶりに思い知った一日であった。
……などと言いつつ、次はサボテンを育てようと画策しているワタシがここにいる。(19960626)
旧よしなしのもくじへ 現よしなしへ
『学校の怪談大事典』など
コンテンツに困った時の「最近読んだ本の話」。
『学校の怪談大事典(日本民話の会・学校の怪談編集委員会編 ポプラ社 1380円)』。ここ数年のブームである「学校の怪談」を、系統立ててまとめた本。現在流通している怪談だけでなく、そのバリエーションやルーツ、関連のありそうな民間伝承にまで言及しているのがすごい。民俗学的・社会学的な視点を持った、資料的にも貴重な本である。もちろん「怪談の本」として読んでも充分コワい。「ターボばあちゃん」はコワくないけど。
『となりのせきのますだくん(武田美穂 ポプラ社 1100円)』。ワタシのイチオシ絵本作家・武田美穂の近作。絵本の筋を紹介することほどつまらないことはないので、ここでは内容は書かない。ぜひ書店で手に取ってほしい。絵がかわいいんだこれ。フキダシやコマ割りといったマンガ的手法を導入するのが最近の絵本の流行りらしいが、ひとつ間違えると「じゃあなんでマンガにしないのか」というハナシになるので難しい。本作はそのあたりの匙加減がちょうどいい。
『日本イカイカ雑誌(全日本イカした雑誌連絡協議会編 竹書房 1300円)』。ごく狭いフィールドをターゲットにした「専門誌」を集めた本。読んで「やられたー」と思った。ワタシも専門誌には昔から興味があって、パソコン通信でも何度か「専門誌さんいらっしゃい」などという連載メッセージをアップしていた。で、このホームページでもそういうコーナーを作ろうと考えていたところだったのだ。くやしい。今やってもマネだと思われるだけだ。やっぱり考えてるだけじゃなくて実行しなきゃ負けだなあ。
紹介されている雑誌は、医学論文誌『胃と腸』だの錦鯉専門誌『鱗光』だの養豚専門誌『月刊養豚界』だのとなかなかディープ。しかしなんといっても貴重なのは、かのアシッドポエム誌『MY詩集』の須田編集長のインタビューが載っている点であろう。文芸くずれの屈折したソウルが伝わってきて、むずがゆい気分になれること請け合いだ。(19960520)
旧よしなしのもくじへ もっとむかしの旧よしなし 旧よしなしのつづき 現よしなしへ
『そこはか通信』タイトルページにもどる
copyright(C)1996-2009 FUJII,HIROSHI all rights reserved.